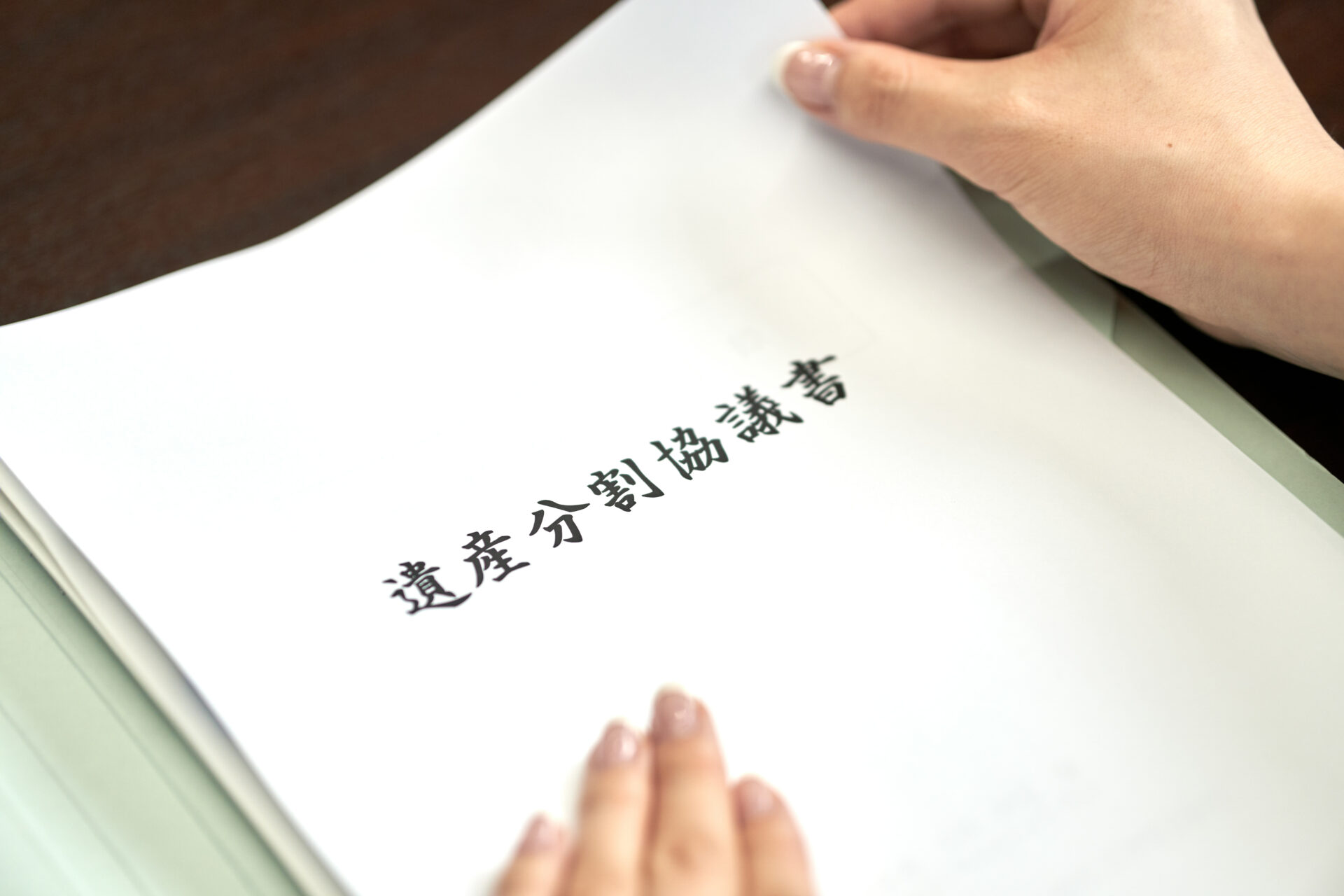相続手続きの中でも特にトラブルが起きやすいのが「遺産分割協議」です。相続人全員で財産をどう分けるか話し合う必要がありますが、もしその相続人の中に後見制度を利用している方(認知症など)がいた場合、注意が必要です。
とくに、その後見人自身が相続人でもある場合には、「利益相反(りえきそうはん)」という法的問題が発生し、そのままでは遺産分割協議が無効になるリスクもあります。
今回は、そんなときに必要となる「特別代理人」について、司法書士としての視点から詳しくご説明します。
利益相反とは?
たとえば、以下のようなケースをご覧ください。
【事例】
被相続人Aが亡くなり、相続人は長男B(後見人)と次男C(認知症、被後見人)。
長男Bが、認知症の弟Cの後見人として、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)を進める場合。
このケースでは、Bが自分自身の利益と、C(被後見人)の利益の両方を主張する立場にあり、利害が衝突する恐れがあります。これを「利益相反関係」といいます。
このまま遺産分割協議書を作成しても、形式上は整っていても法的に無効になる可能性があるため、適切な手続きが必要です。
特別代理人とは?
こうした「利益相反」がある場合、家庭裁判所に申し立てて、中立的な第三者を「特別代理人」として選任してもらう必要があります。
特別代理人とは、被後見人の法的な代理人として、本人の利益を守るために特定の法律行為(この場合は遺産分割協議)を代わりに行う人です。司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることも多く、当事務所でもその支援を行っています。
特別代理人が必要になる典型的な場面
- 成年後見人と被後見人が同じ相続人グループにいる場合
- 親が未成年の兄弟姉妹の親権者で、どちらも相続人である場合
- 被後見人の財産を後見人が購入する場合(例:不動産売買)
- 後見人が遺言執行者で、相続人との間に利害関係がある場合
特別代理人の選任手続き
誰が申し立てる?
後見人や親族などが、家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行います。
申し立てに必要な書類(例)
- 特別代理人選任申立書
- 利益相反の事情説明書
- 被後見人の戸籍・後見開始審判書の写し
- 財産内容を示す資料(不動産評価証明、預金通帳など)
- 協議内容の案(可能であれば)
- 特別代理人候補者の略歴や身分証の写し
期間の目安
申し立てから選任まで1〜2か月程度が一般的です。その後、特別代理人が協議に参加し、遺産分割協議書を作成します。
特別代理人にかかる報酬は?
特別代理人が司法書士や弁護士などの専門職である場合、報酬が発生することがあります。相場としては、5万円〜10万円程度が一般的です(複雑さにより変動)。
報酬に関する重要なポイント
- 被後見人の財産から報酬を支払う場合:家庭裁判所の報酬付与の審判(許可)が必要です。
- 報酬を他の相続人が負担する場合(例:依頼者負担など):家庭裁判所の許可は不要です。
- 親族が無報酬で務める場合:許可不要です。
なぜ家庭裁判所の許可が必要?
判断能力が不十分な人の財産から報酬を支出する場合は、裁判所が内容の妥当性をチェックする必要があります。被後見人の利益を守るための仕組みです。
当事務所でできること
司法書士福田龍之介事務所では、次のような支援を行っています:
- 利益相反の有無の判断
- 特別代理人選任申立書類の作成支援
- 遺産分割協議前の整理とアドバイス
- 協議成立後の相続登記(不動産名義変更)まで一貫対応
まとめ
- 後見人と被後見人が相続人となる場合、「利益相反」に注意
- 利益相反がある場合は、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てが必要
- 特別代理人の報酬が被後見人の財産から支払われる場合は、裁判所の許可が必要
- 法的に有効な遺産分割を行うためには、専門家への相談が安心です
司法書士へのご相談はお気軽に
司法書士福田龍之介事務所では、富士見市・鶴瀬駅近隣の皆様を中心に、相続・後見・家族信託に関するご相談を承っています。
📍 司法書士福田龍之介事務所
埼玉県富士見市 鶴瀬駅東口 徒歩2分
📞 ご相談・ご予約は049-227-3167 または お問い合わせ よりお気軽にどうぞ!